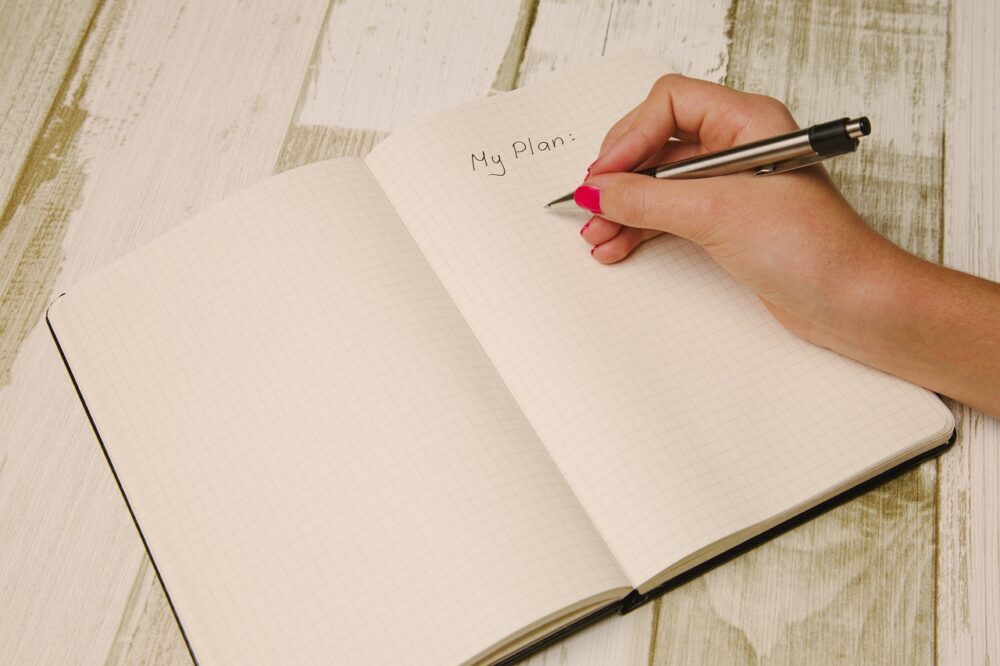
相続前にできること
人が亡くなると、相続人による相続手続を進めていくことになりますが、
生前の準備次第で、理想的な相続に近付けることができます。
下記の手続は、意思能力がしっかりしているときでないと進めることが困難です。
なるべくお早めの対策をお勧めいたします。
遺言
被相続人(亡くなった方のこと)の財産は、相続人が引き継ぐことになります。
被相続人が遺言を遺していなければ、相続人全員の同意のもと、相続財産の分け方を決定すること(「遺産分割協議」といいます。)になります。
遺言を書けば、遺言者が財産の分配方法を定めることができますので、相続人全員による同意をしなくても、相続人は相続手続をよりスムーズに進めることができます。
「自分が亡くなったとき、(推定)相続人は誰になるのか?」
「自分は遺言を書いたほうがいいのか?」
「相続人以外の人に財産を引き継いで欲しい。」
「どの種類の遺言(「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」など)が合っているか?」
「遺言どおりにならないこともある?相続人の『遺留分』とは何か?」など、
ご相談されたい方や遺言の作成を進めたい方は、お気軽にお問合せください。
生前贈与
「相続のときより前に、特定の相手に対して、不動産を引き継がせたい。」
「相続税対策のため、生前に不動産を処分しておきたい。」など、
生前に不動産を贈与したい方は、お気軽にお問合せください。
任意後見契約
任意後見契約とは、
「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約」(任意後見契約に関する法律 第2条第1項 より)
のことです。
分かりやすく言い換えると、「認知症等により判断能力が低下したとき、信頼できる人(任意後見人)に、身の回りに関する法律行為について代理してもらう契約」のことです。
この契約は、意思能力があるうちにしておく必要があります。
判断能力が低下してくると、当人だけでは有効な法律行為をすることが難しくなっていきます。
仮に本人の家族が、本人の“フリ”をして法律行為をしても、その法律行為は無効です。
このようなときに、事前に任意後見契約をしておくと、信頼できる人(任意後見人)に、身の回りに関する法律行為をお任せすることができます。
任意後見契約をしていなければ、家庭裁判所に申立てをして「法定後見人」を選任してもらう必要があります。
「法定後見人」は「任意後見人」と違い、本人や家族が希望する人が選任されるとは限りません。
面識の無い専門家(弁護士や司法書士)が選任されることがあります。
専門家による法定後見人に対しては、毎月費用(目安 3~5万円)を支払う必要があります。
【法定後見に関しては、こちらもご参考ください】
このため、法定後見を避けるために任意後見契約をしておくことが考えらます。
任意後見契約は、公証役場で作成・契約をする必要があります。
司法書士にご依頼いただければ、任意後見契約の文案の作成・契約のサポートをいたします。
お気軽にお問合せください。
民事信託(家族信託)
信託とは、「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること」(信託法 第2条 より)です。
分かりやすく言い換えると、例えば、親のある特定の財産について、子どもが一定の目的に従い、その財産を管理・処分等をすることを言います。そのために、親から子どもへ財産の名義を移す必要があります。
信託についてご相談の方は、お気軽にお問合せください。