遺言作成の勧め 第2回 「作成時の留意点‐遺留分について‐」
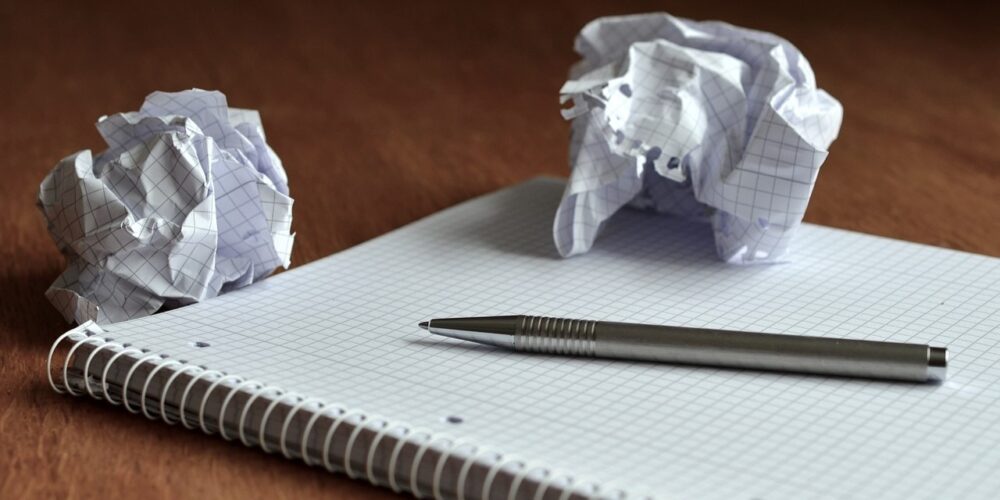
愛知県犬山市/名古屋市丸の内 の司法書士 丹羽一樹です。
以前、こちらの投稿 遺言作成の勧め 第1回 「推定相続人を想定する」 にて、遺言の作成をお勧めいたしました。
今回は、遺言作成時の留意点について触れたいと思います。
今回は、遺留分について触れていきます。
「遺留分」「遺留分侵害額請求権」とは
遺言を遺したい方は、遺言書により自由に自身の財産を承継する者を定めることができます。
例えば、特定の者に対してのみ全ての財産を承継させる旨であったり、承継する者を(推定)相続人ではない者に指定することも当然に有効です。
遺言者が亡くなれば、遺言の内容のとおりに相続財産が承継されますが、遺留分が満たされない相続人がいる場合、その相続人には民法の定める遺留分が認められています。
遺留分とは、一定の相続人に認められている、相続財産に対して一定割合に相当する額を受ける権利です。
*民法
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 (省略)
例えば、遺言者Xが、相続財産全てを相続人ではない者Yに承継させる旨の遺言を遺して死亡し、Xの相続人は妻A、子どもB・Cである場合、次のとおりに考えられます。
遺言の内容のとおりであれば、A・B・Cは一切財産を承継できませんが、代わりに相続財産の2分の1に相当する金銭をYに対し請求することができます。(内訳は、Aは8分の2、B・Cは各8分の1となります。)
これを遺留分侵害額請求権と言います。
また、遺言者Xが、(上記事例の)妻A・子どもBにのみ相続財産を承継させる旨の遺言を遺して死亡した場合、子どもCは相続財産の8分の1(計算方法:Cの法定相続分である4分の1×2分の1)に相当する金銭を、他の相続人に対し請求することができます。
遺留分侵害額請求権は、民法第1048条の定めのとおり時効があります。
*民法
第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
「遺留分侵害額請求権」の性質
遺留分の権利がある相続人が、必ずしも遺留分侵害額請求権を行使するとは限りません。
遺言の内容を尊重して、遺留分を主張しない相続人も少なくありません。
相続人が時効の期間までに行使しなければ、遺留分侵害額請求権は消滅します。
ただし、遺留分の権利がある相続人が被後見人である場合、その相続人の後見人が遺留分侵害額請求権を行使する可能性が高いです。
なぜなら、後見人は被後見人の財産を守る立場にあるからです。
遺言者が留意しておきたい点
遺言の内容は自由では有りますが、遺留分についても想定をしておかないと、理想どおりの遺言内容が実現できない可能性があります。
遺留分が満たない相続人がいる場合、その相続人が時効期間内に遺留分侵害額請求をすれば、財産を承継した者は想定外に金銭の支払を求めらることになります。
対応策としては考えられるのは次のとおりです。
・遺留分が満たされる遺言内容とする
・遺留分が満たされない遺言内容とする場合、財産を承継させたい者が遺留分侵害額請求に対応しやすいように、相当額の金銭も承継させるものとする
・遺留分が満たされない推定相続人の理解・協力が得られれば、その推定相続人に遺留分放棄をしてもらう
遺言作成時の留意点は他にもございますので、第3回に続きます。
遺言作成についてご相談のある方は、お気軽にお問い合わせください。

