相続が起こったとき、信託中の不動産の登記はどうすべきか?
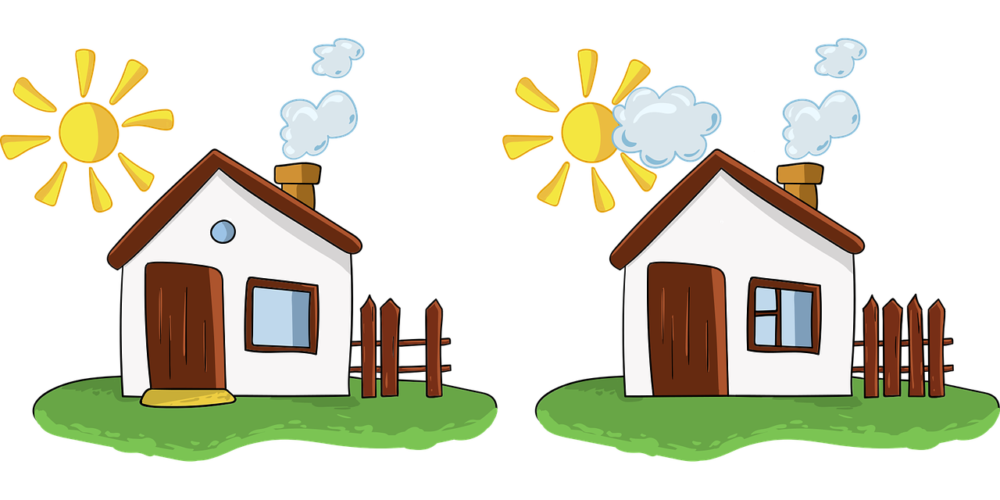
愛知県犬山市/名古屋市丸の内 の司法書士 丹羽一樹です。
先日、受益者死亡により、信託を終了をさせる登記をいたしましたが、登記手続きの流れを構築するのになかなか苦労いたしましたので、備忘録として、今回記事にいたします。
今回の事例
今回の事例は、以下のとおりです。
信託を以下のとおりに組んでいた不動産(以下、「信託不動産」と言います。)がございました。
委託者兼受益者→A、受託者→B、帰属権利者→B
信託の目的としては、よくあるケースで、A・Bは親子であり、A名義であった不動産は、信託を原因としてB名義となり、Bはその不動産の処分・管理権限が与えられるも、それはAの利益のために行うものとなります。
(認知症対策として、AB間でこのような信託契約を行う方法があります。)
そのため、その不動産の名義はB名義であるものの、売買や贈与等の理由で名義を取得した場合と異なり、Bには「受託者」という肩書が付きます。(分かりやすく言うと、「全く自由に処分等ができる所有者」と異なり、「信託契約で定めた目的の範囲内での権限が付された所有者」を指します。)
それに対し、委託した側を「委託者」、信託財産からの利益を受ける者を「受益者」といい、この「委託者」と「受益者」は本ケースのように、同一人であるケースが多いと言えます。
今回、信託不動産は、Aの生前にBによって売買などされないまま、Aが亡くなりました。
ちなみに、Aには信託をしていない不動産(以下、「相続不動産」と言います。)も有りました。
信託中、受益者が亡くなった場合、信託不動産はどうなるか?
相続不動産は、いわゆる「相続登記」をすることになりますが、信託不動産は、「相続登記」の対象にはなりません。
そもそも、信託不動産は相続財産ではないため、以下の点に注意する必要が有ります。
・遺産分割の対象にはならないため、相続人間で引継ぎ方を自由に定めることはできない。
・後に売却をしても、「空き家の3000万円特別控除の特例」を受けられない。
では、受益者が亡くなったとき、信託不動産がどのように取り扱われるかは、信託契約の内容に基づくことになります。
信託の終了事由として「受益者の死亡」の定めがある場合には、信託は終了となります。そして、それを登記簿に反映させることになります。
私の感覚としては、相続登記と異なり、信託終了の登記手続は一般の方では少々対応が難しいかと存じます。実際、今回、私が取り組む際もかなり悩みました。。。
今回の対応(ここからは専門的な内容となります)
信託が終了しても、例えば「信託終了を届出するだけ」ということでは済みません。
信託が終了となれば、その終了時点で残っている信託財産(「残余財産」と言います。)を清算していくことになります。
「会社が解散した後、清算手続をする」というイメージと同じです。
誰がそれを行うかと言うと、「清算受託者」によって行うことになります。(「清算受託者」は、受託者と同一人としている信託契約がほとんどです。)
「残余財産」に関しては、信託契約において「帰属権利者」という者を定め、その者に帰属させるという定めをしているケースが多いです。
今回は、以下の登記をしていくことになります。
・受託者名義から帰属権利者名義への変更
・信託の目的不動産が無くなることによる、信託登記の抹消
※信託登記特有の問題点
不動産を対象とする信託契約をした当初、それを基に登記申請をすることになります。
登記事項として「委託者」「受託者」「受益者」は明確に登記されますが、それに加えて「信託目録」という事項も登記します。「信託目録」の内容についても一定のルールは有るものの、率直言えば、そのルールには“曖昧さ”が有ります。そのため、申請した内容のまま「信託目録」の登記が通るものの、後に、「登記されてる『信託目録』のままでは問題有り」という扱いを受けることも有ります。
(1)信託目録の更正
今回、信託目録に「清算受託者」「帰属権利者」の定めが明確に記載されていなかったので、まずは信託目録にその定めを入れるように更正を求められました。
「錯誤」を登記原因とする登記原因証明情報を作成して申請することになります。
(2)受益者の変更
(令和6年1月10日付民事二第17号に基づく)
受益者Aの死亡により、信託は終了し、信託法第183条第6項に基づき、信託清算中の受益者は、「帰属権利者」となります。
そのため、受益者を(帰属権利者である)Bとする変更登記をします。
「受益者Aの死亡」を登記原因とする登記原因証明情報を作成して申請することになります。
(3)受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記の抹消
これまで“受託者”B名義となっていた信託財産ですが、Bは受託者としてではなく、信託終了により、完全に財産を引き継ぐ“帰属権利者”としての名義人となります。
そのため、Bの固有財産となった旨の登記をします。
同時に、信託の効力は無くなることになり、信託登記の抹消もします。
「信託財産引継」を登記原因とする登記原因証明情報を作成して申請することになります。
なお、帰属権利者が委託者の相続人であれば、登録免許税法第7条第2項の軽減措置の適用を受けます。
(4)注意点
※受託者が信託財産を固有財産とするには、受益者との関係で、利益相反取引に該当しないことが必要です。本事例では、「受益者の死亡により信託が終了した場合の清算受託者及び帰属権利者は、信託終了時点の受託者とする」旨の定めがあるため、信託法第31条第2項第1号により、利益相反取引に該当しないと考えられるため可能となります。そのためにも(1)の信託目録の更正をして、その定めを示す必要が有りました。
※(2)については、その登記を経由しない考え方も有ります。しかし、その場合、(3)の登記を申請する際に、Bのみでは手続はできず、受益者Aの相続人全員が登記義務者となります。つまり、Aの相続人全員が、印鑑証明書を提供して申請手続に参加する必要が出てきます。
※(3)の登記では、Bのために新たに登記識別情報が発行される訳ではないため、信託登記をしたときの登記識別情報をそのまま有効なものとして取り扱う必要があります。
信託したまま、相続が起きたことについて
人は皆、将来のことは分からないため、後から(相続があった後)に「認知症対策として信託をしたことは正解/不正解だった」という判断をすることは、(つい考えてしまうとは思いますが)意味が無いことかと思います。
信託した時点で、「認知症対策を講じた」という安心感を持てるため、その時点で既に信託の意味があったと言えます。
ただ、やはり、信託したまま相続が起きると、費用や時間をかけた割に無駄(場合によっては逆効果的)と捉えてしまうことにもなりかねないため、「親の年齢」「売却の可能性」を比較して取り組まれることをお勧めいたします。
(もちろん、信託は、認知症対策以外の目的でも組むことは有ります。)
不明点があれば、ご相談ください
- 信託された不動産の登記がよく分からない
- 受益者が亡くなった後、どのように登記を進めればよいか不安
信託登記の実務は、通常の相続登記とは異なる視点と処理が必要です。
不安な点があれば、ぜひご相談ください。

